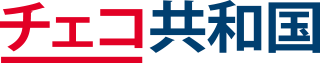<エッセイ>ボヘミアは海辺にある
チェコは読書家が多い国です。以前2016年に発表された世界の読書時間ランキングでは6位に輝き、日本の1.8倍もの時間を読書に充てているとの結果もでています。
それは、数多くのすぐれた文学作品がチェコで生まれているからかもしれません。以前にこのブログでもご紹介しましたカレル・チャペックをはじめ、ボフミル・フラバル、ミラン・クンデラなど著名な作家はもちろんのこと、現代の作家たちも世界で高い評価を受けています。
そんなチェコの作品が日本に広く知られるためには、翻訳が欠かせません。
今回は、若手翻訳家のためのコンクール「スザンナ・ロート翻訳コンテスト」の2018年大会で優勝した島田淳子さんに寄稿いただきました。
ボヘミアは海辺にある
島田淳子
二年前のちょうど今頃、わたしは二度目のチェコ留学の途についていた。2014年9月に同地で初めての留学を終えて以来、わたしはずっとチェコに「帰る」日を待ちわびていた。チェコ語はかなりできるつもりだった。外国人のためのチェコ語講座では最上級クラスで勉強していたし、2014年にチェコの作家ボフミル・フラバル翻訳コンテストで賞を取ったことを、ちょっぴり鼻にかけてもいた。前回の留学の間に現地の友達もたくさんできた。論文執筆と学会発表に追われる日本での日々を振り払って、わたしはチェコ社会にどっぷり浸かり込んでやろうと思っていた。
けれども久しぶりに降り立ったチェコの様子は、随分と変わってしまっていた。友達の多くは既に大学を卒業し、仕事を始めていた。前回の留学を終えるころ「絶対にまた戻ってくる」と言い張るわたしに、あるチェコ人の友達が「君は二度と同じ場所に帰ってくることはないんだよ、川の水は流れてゆくからね」と言っていた。それが『方丈記』からの引用なのか、それとも、チェコでも同じような言い方をするのか聞きそびれたまま、彼はドイツに移り住んで、連絡が取れなくなってしまった。
街は何となく以前よりピリピリしているように感じられた。2015年にヨーロッパ全土を揺るがした難民危機が、その大きな原因だったと思う。冬の日に静電気が指先を走るように、ほんの時折、冷たい視線に突き刺されてはっとすることがあった。いつだったか行きつけの居酒屋で、常連のおじいさんがわたしをつかまえてイスラムヘイトをぶちまけたことがある。反論するわたしの言葉尻をとらえて、彼は言った。
「チェコ人はそんな表現せんのだよ」
わたしはグラスを飲み干して店を出た。以来店からは何となく足が遠のいてしまった。
数年前、日本語とドイツ語で活動する作家の多和田葉子が、大阪で開かれた朗読会で「わたしたちには顔の訛があるから、時に言葉の訛が目立たなくなる」と言っていたのを思い出す。顔の訛の陰から尻尾を見せる言葉の訛をあげつらわれて、わたしは吃音症にかかったように、口元をひきつらせてチェコ語を話すようになった。
映画館アトラスで、わたしはひとり、スウェーデン映画の『サーミの血』を観ていた。ウプサラのスウェーデン人社会に入り込もうとするサーミ人の少女の姿に自分を重ね合わせながら、わたしも彼女と同じように自分をすり減らしていた。わたしはチェコ人になろうとしていたのかもしれない。

そんな葛藤を振り切れぬまま、わたしは二年目の冬を迎えた。肌を切るように冷たい風と、雪。午後3時には日は暮れはじめ、待っているのは長い長い夜。図書館で取り寄せた資料に目を通しながら、日がな一日進まない論文をつつき、週に数回専門分野のゼミに出ては、自分の能力のなさに打ちのめされる。図書館のクロークのおばさんと守衛さんだけにはひどく気に入られて、一日の始まりと終わりに彼らと世間話をするのが、わたしのささやかな楽しみだった。わたしはふと、イェチュナー通りにあるプラハ文学館に招かれた、ドイツの若い女性作家のことを思い出す。学生時代にプラハに半年留学したことがあるという彼女に、司会者は尋ねた。
――プラハでの留学はどうでしたか?
――そうね……留学生活は孤独だったわ。
――まぁ、どうして?
――あら、素敵なことじゃない。
なかなかそうは思えないな、と思いながら、寒空の下わたしは家に帰る。
わたしがスザンナ・ロート翻訳コンテストに応募したのは、まさにそんな最中だった。少年漫画のようにアップテンポな書きぶりに、個性的なキャラクター。国立図書館の閲覧室を統べる静けさの中で、アルファベットの隙間から飛び出してくるファンク・ミュージックの野性的な響きに耳を傾けながら、わたしは思わず笑みを浮かべる。作品の面白さと、それを日本語に移し替える快感に、わたしはただただ身をゆだねていた。

7月、各国のスザンナ・ロート翻訳コンテスト受賞者とともに、ズリーンで開催されたボヘミスト向けのワークショップに参加した。世界中のチェコ文学の専門家が集うそのワークショップで、ベテラン研究者たちは駆け出しのわたしたちに、気さくに声をかけてくれた。ボヘミストたちは、若手のチェコ研究者にオープンだ。彼らは自分たちが大きなコミュニティではないことを知っている分(ワークショップの参加者は、大型バスひとつに収まってしまうほどだった)、新しい仲間を心から歓迎してくれる。
とりわけホテルで同室だった韓国出身のボヘミストとは何でも話せる親友になった。しっかり者の彼女は、時々抜けているわたしに、いつも絶妙なタイミングで合いの手を入れてくれる。ふたりしてチェコ語で話す姿を見ながら、ズリーン市立美術館の学芸員の女性は嬉しそうに微笑んだ。
「あなたたちふたりがチェコ語で話しているなんて、なんだか不思議で……」

そう、チェコ語がわたしをつないでくれたのは、チェコ人だけではない。チェコ人自身が、時に自分たちの言語をあまりに小さな言語だと思いこんでいて、わたしは切なくなることがある。もちろんそれは、英語やドイツ語、フランス語のようなメジャー言語と比較すれば、厳然とした事実なのだけれど。けれどもこの言語は、少なくともわたしにとって、世界とつながるための窓口だった。
Thou art perfect then, our ship hath touch’d upon
The deserts of Bohemia?
シェイクスピアの『冬物語』にあらわれる「海辺のボヘミア」のイメージは、20世紀に入ってチェコや隣国ドイツの様々な作家にインスピレーションを与えた。オーストリアの詩人インゲボルク・バッハマンは、自由化の波が高まる1960年代のプラハを訪れて「ボヘミアは海辺にある」と題した詩を書いている。また、わたしが研究するプラハ出身のドイツ語作家リブシェ・モニーコヴァーも、この文学的トポスに基づいてボヘミアの国境線を移動させるという挑発的なエッセイを綴っている。彼女の作品を読みながら、わたしは、チェコはチェコの国境線の内側だけにあるわけではないということを知った。

わたしは、チェコを旅に連れ出したいのだと思う。わたしを海の外へと連れ出してくれた代わりに。文学を通して、翻訳を通して、遠く極東の海辺へと。これまでにチェコと日本をつないできた数々の翻訳作品と一緒に、日本におけるチェコの世界を少しずつ広げていくことができれば……そう思いながら、わたしは再び二年間の留学を終えて、大阪に降り立ったのだった。

※若手のための翻訳コンンテスト「スザンナ・ロート翻訳コンテスト」は、世界各国のチェコセンター及びCzech Literary Centreの共催で毎年開催されています。
2019年大会の詳細は決まり次第チェコセンターのウェブサイトに掲載いたします(2018年12月~2019年1月ごろ)。